今回の記事について
リフォーム営業で様々な建物やお客様に出会ってきました。
リフォームに大きな夢を抱いたお客様とお会いしてお話を伺いますが、
建物によっては要望が叶えられなかったり、できることが限定されてしまったり、
リフォームを断念される方も実は多くいらっしゃるのです。
その事実をお伝えするのは非常に心苦しく慣れないものですが、
リフォームをこれからお考えの方や、リフォームをして住むための中古物件を探している方、
将来リフォームして長く受け継いでいくことを前提に新築される方に、
知っていただきたいことをまとめたいと思います。
「リフォーム前提で中古物件を購入したが間取り変更ができない」
「気に入ったリフォーム会社にお願いしたいが断られた」
「新築で建てたメーカーでしかリフォームできないと言われた」
こういった事がリフォームでは起きることがあります。
何故そうなるのか、丁寧に解説してくれるリフォーム会社もそう多くはないでしょう。
今回は建物別にリフォームにおいて注意すべき点をまとめていきます。
型式認定住宅(工業化住宅)
型式認定については大変分かりやすくまとめられている記事がございましたので、
引用させていただきます。是非こちらの記事をご覧ください。
型式認定工法って何?メリットとデメリットをわかりやすく説明します – 注文住宅、家づくりのことならONE PROJECT
超簡単に言うと、ハウスメーカーオリジナルの住宅です。
認定を受ける事で申請等簡略化でき、差別化しつつコストを抑え量産できるといったメリットがあります。
工業化住宅やプレハブ住宅と言ったりもするようです。
型式認定住宅だった場合、基本的には建てたハウスメーカー以外でのリフォームは難しくなります。
ハウスメーカー独自の工法で認定を取得している住宅になりますので、
他社にはその内容が分かりませんし、下手に手を付けると問題が起きる可能性もあります。
保証を出すのも難しく、リフォームを請ける会社としても大きなリスクとなります。
他社でリフォームをする場合、できても内装のリフォームや設備の取り替え程度です。
会社によってはそれすら断られる場合もあります。
間取りの変更や窓の交換など大規模なリフォームはまずできません。
建てたハウスメーカーにお願いするにしても、他社との金額の比較ができないので、
相場感も分からず高めの単価設定になっている可能性もあります。悪く言うと囲い込みですね。
日本には伝統的な工法である在来工法(木造軸組工法)がありますが、
在来工法であればこういった問題は起きません。
ハウスメーカーでも在来工法で建てられるメーカーもありますので、確認してみるといいでしょう。
型式認定住宅にももちろんメリットはありますので、
双方のメリットデメリットと今後その建物をどうしていきたいかを踏まえた検討が必要です。
これから中古物件を購入される方も、型式認定住宅を購入すると思ったようなリフォームができないといったことが起きますので注意が必要です。
個人的な意見としましては、私が家を建てるなら型式認定住宅は避けます。
建材も長寿命化が進んでおりますので、次世代まで引き継いだり、
売却や賃貸で残していくことが今後より一般化していくと思われます。
そんな中、リフォームができる会社が限られたりできる事の制限がかかることは大きなデメリットだと考えています。
在来工法でも質のいい住宅は建てられますし、新築したハウスメーカーが潰れないとも限らないですしね。
以上余談でした。
2×4(ツーバイフォー)工法
次に2×4工法です。木造枠組壁工法ともいいます。
2×6工法を扱う会社もありますが、お伝えすることは同じですので、見出しは2×4工法としております。
2×4も住宅もリフォームの際には注意が必要です。
2×4工法は在来工法とは違い、建物を面で支える工法ですので、建物の壁ほとんどが耐力壁になります。
簡単に言うと、壁のほとんどが構造上大事な壁になります。
ですので、間取りを変えたり、壁を抜いたり、窓の位置を変えたりするリフォームは、難しくなります。
2×4工法は新築時に構造図を作成し、基本的には新築時メーカーが保存しています。
確認申請時に構造図や構造計算書を添付する場合もありますが、
その書類が無いと他社で構造の検討ができませんし、
そもそも2×4工法の構造検討ができない会社もあります。
2×4であれば、設備の交換や内装の交換程度しかできない会社も多くありますので、
あまりリフォーム向きの工法とは言えません。
2×4工法の中古物件も市場には多くありますので、購入してリフォームをご検討される場合は、
できることがかなり限定される場合がありますので注意が必要です。
2号・3号建築物
まず、2号・3号建築についてですが、
2号建築物:木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが2mを超えるもの
3号建築物:木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
こういった建物になります。
街を歩いていてもよく見かける建物ですよね。
こういった建物は新築時に提出する確認申請に構造計算書を添付しなければならない部類の建物になります。
例えば、築20年を迎え間取り変更を伴うリフォームをする場合、
新築時の構造計算書と図面を元に、間取りを変えても安全性に問題無いかを計算する必要が出てきます。
リフォームの営業をしていて、こういった建物のリフォームを検討されている方は多くいらっしゃいますが、
新築時の書類は捨ててしまった、無くしたという方、結構いらっしゃいます。
確認申請を提出した際に手元に残る副本は施主が受取りますので建てた業者は基本的に保管していません。
構造計算書は確認申請の副本に綴じてありますので、
そういった書類が無いと、構造計算のしようがなという事態になります。
つまり、間取りの変更など、構造に影響するリフォームが出来ないということです。
一から構造計算をし直すにしても、柱や耐力壁の場所が正確に分からないと計算はできませんので、
実質再計算もかなり困難になります。
最後に
今回はリフォーム営業をしていて、思わず身構えてしまう建物を挙げてみました。
思い切ってリフォームしたいけど、建物の都合で叶わないこともあるという事を知っていただければと思います。
昨今、中古の家を購入してフルリフォームする方も増えてきています。
せっかく買ったのに理想の住まいが実現できないなんてことは避けていただきたいので、
事前にしっかりと調べた上でご判断いただければと思います。
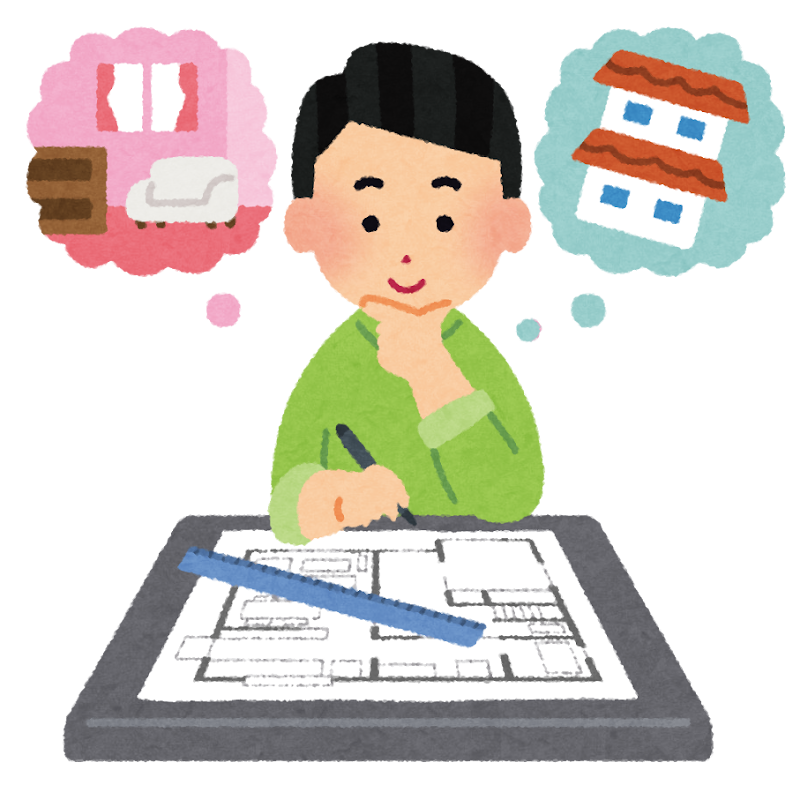


コメント|comment