リフォーム日記 着工〜解体初期編
自邸のリフォームについて、これまでVol.1〜Vol.3まで、
考えるのに苦労した動線について記事を書いてきました。
Vol.1↓
Vol.2↓
Vol.3↓
実際に苦労してきたことは、動線以外にも「収納スペース・収納量」「エアコンの設置場所」
「空間デザイン」などがあります。
夫婦で考えているので、意見の相違やデザインの好みなどが違う部分もあり、
方向性を決めるのにも一苦労です。
実際に自邸のリフォーム計画をすることによって、
仕事ではできない体験をできたと思います。
私は、リフォームの担当をしている時、基本的にはお客様のご要望やご意向を
最大限に汲み取り、それを計画に反映するように努めてきましたので、
自分の意思を貫き通すようなことはほとんどありませんでした。
初めて自身がお客様の立場になり、
「自分ごと」として色々な苦労を経て、やっと2025年2月に着工まで辿り着きました。
着工から約5日経過した現在、解体工事の真っ最中です。
これからは、現場の進捗などを記事にして、皆様にお伝えしていければと思います。
完成→実際に住んでみて の感想も記事にしたいと思っておりますので、
今しばらくお付き合いください!
皆様のリフォーム計画の参考になれば幸いです!!
着工前の準備
家の片付け
リフォームを経験した方はすでにご存知だと思いますが、
着工を目の前にして1番大変なことは、「片付け」です。
大規模なリフォーム、小規模なリフォームにかかわらず、
工事の為に「現場」となる場所をきれいにお片付けをする「業務」がのしかかってきます。
リフォームをされる方には、それぞれ色々な理由があるかと思います。
例えば
・親御さん(お子様世帯)と2世帯住宅にするためのリフォーム
・両親が他界し、相続して住むためのリフォーム
・新築から年数が経ち、綺麗にするためのリフォーム
上記以外の理由でリフォームする方もいるでしょうが、
どのリフォーム形態においても、片付けがつきものです。
簡単に「片付け」と一言で表しましても、
ましてや、自分だけでは判断できないもの、残しておかなければいけないものの選別など、
ただ処分するだけではありません。
今回、私の場合は、
「祖父母が他界し、相続して住むためのリフォーム」
「新築から年数が経ち、綺麗にするためのリフォーム」
の二つに該当します。
そのため、特に祖父母の残していったものの処分判断にかなり時間を有しました。
勝手なイメージですが、私の祖父母くらいの古いの世代の方々は
物を大切にとっておくケースが多く、その分荷物もかなり多い印象です。
実際、私が担当したお客様でも、
祖父母の家のリフォームの際は頭を抱えられる人がたくさんいました。
リフォーム計画の打ち合わせを行うのにも時間はかかりますが、
リフォームすることを決めた方は、なるべく早めにお片付け計画を立てることお勧めします。
また、業者に処分品の引き取りを依頼するには、お金がかかります。
量にもよりますが、15万〜40万は平気でかかってきます。(解体費用とは別途で…)
お金が有り余っている方は以外は、計画的に粗大ゴミで処分するのが賢明です。
今回の私同様、祖父母からの相続でリフォームされる方は、
骨董品・アンティークなども出てくるかもしれません。
リフォーム後の家に飾ったりしない場合は、査定してもらうのもいいと思います。
ちなみに、象牙等はワシントン条約に引っかかるので、気をつけましょう。
環境省HP:https://www.env.go.jp/nature/kisho/zougetorihiki.html
引越しまで
いざ、片付けが終わったら次は引越しです。
引越しに関しては、引越し業者さんに頼む方がほとんどと思いますが、
着工のタイミングを合わせるのはもちろん、
繁忙期を避けるなどすると費用を抑えることができるケースもあります。
繁忙期か繁忙期じゃないかで、10万円ほど変わることも。
高級家電が買える金額なので、是非計画段階から担当者に相談してみてください。
早めに引越し業者を抑えるのもいいでしょう。
引越し前には、必ずご近隣の方々へご挨拶しておきましょう。
工事期間は騒音や振動でご近隣へ迷惑を掛けることが多々あります。
クレームなどで工期が伸びてしまうこともありますので、
やれることはやっておくことが、スムーズな工事に繋がります。
担当者にお願いすれば一緒に回ってくれたり、
完全にお任せすることもできるかもしれませんので、
事前にご確認いただくのがいいと思います。
また、見落としがちなのが「ゴミ当番・回覧板」。
地域によっては、ゴミ回収後の清掃やネットを戻す作業など、
当番制になっている地域もあるかと思います。
仮住まいでリフォームされる方は、事前に町内会に申し出たり、
お知り合いに当番を変わってもらう必要がありますのでご注意を。
近隣挨拶の際、一緒にその旨を誰かに頼むのもいいかと思います。
ここまでできたら片付けの最終段階です。
家の中が終わったと安心している方、外回りにご注意ください。
大規模なリフォーム、外装工事を伴うリフォームになると、
足場を組み立てる必要があることも多いです。
その際、植木や置物が邪魔にならないか、物置が邪魔にならないかなど、
家の外の片付けにも意識を向けるとGoodです。
解体開始(フルスケルトン工事)
基本的にリフォーム解体は重機は使用せずに、職人の手壊しになる場合が多いです。
新築とは異なり、既存の建物を残して工事が行われますので、
あまり大きな機材は搬入が難しいのと、
残す場所、壊す場所が細かく分かれますから、
手壊しの方が効率がいいという側面もあります。
そのため、新築するための解体よりも場合によっては工事に時間がかかります。
リフォーム内容によっては、
既存の部屋を残したり、思い入れのある壁や天井を残したりすることもあるでしょう。
残す部分が多くなればなるほど、それ相応の時間がかかると考えてください。
素人考えとはギャップが生まれてくる部分になりますので、
工事内容・工事方法を把握したうえで、ご理解いただけるといいと思います。
時には寛大な心で受け入れてあげましょう。
解体手順
現在、ちょうどわが家の解体途中なので、写真を用いながらご説明します。
職人の手壊しで解体をおこなっていきます。
フルスケルトン工事の場合は内装の解体から始まります。
皆さんのご想像通り、屋根・外壁から壊してしまうと、
雨風が家の中に容易に入ってきてしまうからです。
そのため、内装から壊していくのがセオリーです。

コチラは解体2日目の写真ですが、1階の床は残して壁・天井の解体が
ほとんど終了しておりました。
床は石膏ボードの粉や埃で白くなってますが、オークの床材はまだ存在しています。
床は、職人の足場を残し作業効率を上げるためにの最後に壊すのが一般的です。
基本的に工事は上から行っていくのが良いとされている理由もその一つです。
解体すると中の構造がわかってきます。
ちなみに上の写真からは、
「筋交がしっかり入っているか」
「筋交の寸法」
「柱のサイズ」
「金物補強されているか」
など、構造に関する情報を読み取ることができます。
リフォーム特有ですが、解体してからでないと詳細な構造が確定できないことが多々あります。
新築時に図面通りの工事がされていない可能性や、
違う寸法の材が入っている場合も多いからです。
計画段階の打ち合わせで、耐震診断や構造計算を行なっていたとしても、
解体後に再度確認・計算を行う必要があります。
場合によっては、追加で補強を行わなくてないけないケースや、
最悪、元々計画していたPLANが実行できない なんてことも。
しかし、「構造」は建物の要です。
今後安心してご生活するためにも、
この解体の段階で、しっかり確認してくれるメーカーさんは頼りになりますね。
解体中のトラブル
実際に解体して、問題が発生しました。


シロアリ被害と雨漏りです。
シロアリ被害は、解体してわかるパターンと、
家の中に発生したシロアリを目視して、事前に被害がわかるパターンがあります。
私の場合は後者でしたが、柱の上の方までシロアリ被害がありびっくりしました。
柱はスカスカになっており、非常に脆くなっておりました。
しかし、被害は柱1本だけで留まっていたため、最小限被害で何よりでした。
深刻な場合、被害が全体に広がって、至る所に蟻害(シロアリ被害)が発見されることもあります。
定期的な防蟻処理はしっかりと行うのが、大切だと再認識しました。
雨漏れに関しては、表面のクロスに雨染みが出てなかったこともあり、
気づいていなかった部分でしたが、解体して原因追求することができました。
雨漏れは原因を解決しないと折角リフォームをしても再発してしまいますので、
解体の際に原因確認、修繕をして解決することが大切です。
他にも解体の写真をご紹介します。

窓周りの解体写真

ダイニングキッチンの解体写真

階段下の解体写真

天井解体写真
壁には断熱材が入っていいますが、湿気によるカビの発生でどれもこれも黒ずんでしまっています。
湿気を吸うと断熱効果が弱まりますので、今回は交換工事を行います。
天井には大空間を作るために、鉄骨の柱が入っていました。
まとめ
今回は解体の初期段階のご紹介をさせていただきました。
今後解体が終わると、大工工事に進んでいきます。
今後もリフォーム日記として、進捗をお届けしていきますので、
ぜひ楽しみにしていてください。
それではまた。



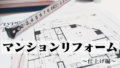
コメント|comment